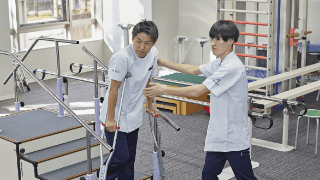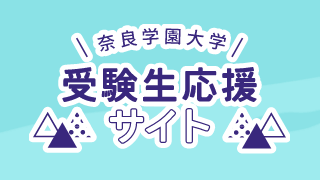人間教育
学科-
- 准教授
- モリセ トモコ 森瀬 智子

プロフィールを教えてください
- 音楽専修の教員です。声楽、合唱、音楽教育を専門とし、中等音楽教員に必要な授業だけでなく、小学校教員に必要な音楽科の授業も担当しています。国公立の中学校、中等教育学校に長年勤務した後、保育士教員養成校で声楽や音楽表現、教職論を担当する教員として勤務し、奈良学園大学に勤めて5年目になります。中学校や中等教育学校では、合唱部の顧問を務め、指導・指揮者として何度もNHK学校音楽コンクールの全国大会や全日本合唱コンクールの全国大会にも出場し、受賞いたしました。現在は複数の合唱団で常任指揮者を務めており、幼児から大人まで数多くの合唱団の指導に携わっております。その他、全日本音楽教育研究大会全国大会のアドヴァイザーや音楽科研究会や合唱講習会の講師を務めるなど、音楽科教育と歌唱を柱に活動しております。
どんな研究をされているのですか?
-
主には現在二つの研究を進めています。
一つ目は、国公立の中学校、中等教育学校や保育士教員養成校に勤務した経験を活かして、幼児から中高生までの歌唱を主とした音楽表現とその指導法を研究しています。その中でも特に、発声の違いから生み出される合唱表現の違いの研究のため、小学校、中学校、高等学校へ出向いてアプローチを変えて指導することで、どのような変化が生まれるのか、実際何度も出向いて研究を進めています。
二つ目は、協同学習を用いた音楽科における表現力の育成についてです。教員の専門分野や技能によって差のでない鑑賞領域や創作分野について、協同学習を用いることで楽しく表現力をつけることのできる授業指導方法です。これについてはゼミでも学生と共に進めることもあります。 -

今の研究分野に興味を持つきっかけやエピソードを教えてください
-
上記の一つ目の歌唱の発声については、教員として合唱部を指導していた際に、発声学会をはじめとし、様々な場所へ出向いて勉強を進めたことがきっかけになっています。
二つ目の協同学習を用いた表現力育成では、教員として神戸大学附属中等教育学校に勤めたことがきっかけです。この学校では、赴任した一日目から指導法の研究の研修があり、その時に初めて知ったのが『協同学習』という科目の指導法でした。今の主体的な深い学びに繋がる教授法なのですが、その方法が50年以上も前から行われていたことに衝撃を受けました。やっと時代が追い付いてきた感じですが、私も生徒の時にこの方法で学びたかったと強く感じました。『協同学習』を学んだことで、教員の教材研究と指導法の研究の重要性を強く感じました。
担当している授業の中の1つを紹介してください
- 合唱Ⅰ・Ⅱ
合唱Ⅰ・Ⅱはどんな授業ですか?
-
まず、30分間は良い声を出すための呼吸法と発声を行います。その後、基礎練習となるコールユーブンゲン、コンコーネの教則本を用い、音符への対応力を高めます。その後、合唱曲をパート練習→全体合わせ の順に行います。
アカペラの曲や伴奏の付いている混声三部、混声四部の曲を扱います。
その際、実際教員になった時や、教育実習へ行った時のことも考えて、合唱を授業で行う際の注意点や指導法についても説明します。
また、指揮者も全員順番に経験してもらい、合唱指揮の注意点についてお話しします。みんな合唱の際は座学では見られないほど生き生きした表情で、それが音楽の良さだと感じております。
授業外ですが、学内の演奏会では合唱を披露します。 -

趣味や特技など好きな休日の過ごし方などを教えてください
-
歌うことと読書(話題になっている本)、ハーブを育てることです。
昨年から自分で決め、毎年リサイタルを行っているのでその練習をしています。舞台ではアンサンブルもあるため、教え子で現在活躍中の歌手の方と一緒に歌える時間は至福の時です。
読書は、専ら学内の図書室のおすすめ本を読んでいます。先日は図書室のスタンプラリーの結果、オードリーヘップバーンさんがプリントされた栞をいただき大満足でした。
家のベランダはハーブだらけです。というかハーブしかありません。特にお気に入りはアロマデュカスです。とても香りが良く、いつも癒されています。病気や害虫にも強く、どんどん増えています。しかし、今は増えすぎており心配しています。