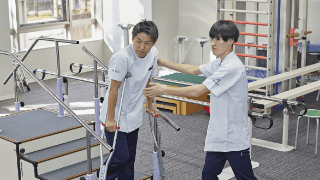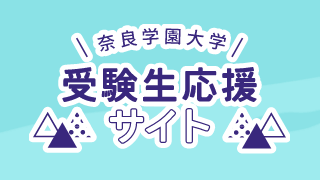人間教育
学科-
- 講師
- オオタ カツヒサ 太田 雄久

プロフィールを教えてください
- 大学卒業後、大阪府下の小学校で教師としてのスタートを切りました。初任校の先輩の先生から声をかけていただいたことがきっかけで、理科の授業研究を行うようになりました。そして数年後、国立大学附属小学校で本格的に理科の授業研究を行うことになりました。国立大学附属小学校に勤めていた頃は、小学校で児童の指導や理科の授業研究を行うことはもちろんのこと、その他にも教育実習生の指導や大学の授業も担当しました。小学校の教師でありながら、大学生の指導や大学の教育に関わること、言い換えれば教員養成に関わる機会が多くありました。教員養成に関わることについての関心が出てきた頃、縁あって奈良学園大学で大学教員としてのキャリアをスタートすることになりました。
どんな研究をされているのですか?
- 学習指導要領で示されている「持続可能な社会の創り手」の育成するために、学校ビオトープを活用した新たな教育活動に取り入れられるかということについて研究しています。これまで学校ビオトープは環境教育の中で取り扱われており、たくさんの教育的な効果も実践を通して得られています。このような学校ビオトープを、環境教育という枠組みではなく、現行の学習指導要領で示されている「カリキュラム・マネジメントの充実」や「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」、「合科的・関連的な指導」などの観点やESD(持続可能な開発のための教育)の視点からとらえ直すことで、特に小学校教育における学校ビオトープを活用した教育活動の開発を目指しています。
今の研究分野に興味を持つきっかけやエピソードを教えてください
- 今の研究分野に興味を持ったきっかけは、大学院博士課程の受験です。現在、指導してくださっている指導教員の先生と博士課程での研究テーマについて話していく中で、学校ビオトープを活用した教育活動への魅力を感じました。これまでは、学校ビオトープに関する研究や教育実践を行ったことはほとんどありませんでした。学校ビオトープに関する研究を行うことで、自分自身の研究の幅も広げることができるとも考えています。
担当している授業の中の1つを紹介してください
- 理科指導法
理科指導法はどんな授業ですか?
- 子どもが主体的に学ぶ理科の授業のつくり方やその授業の中での教師の関わり方について学びます。授業のつくり方については、現行の小学校学習指導要領の内容や理科教育に関する理論などを理解しながら学んでいきます。また、教師の関わり方については、主に模擬授業(学生が考えた理科の授業を実践すること)を通して学んでいきます。理科の授業は他の教科とは違って「観察、実験など」の学習活動が必ず伴います。けがや事故がなく安全に「観察、実験など」の学習を行うために留意することを考えることもとても重要です。
趣味や特技など好きな休日の過ごし方などを教えてください