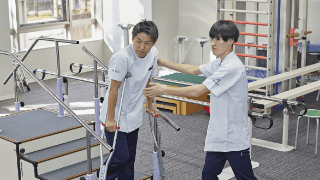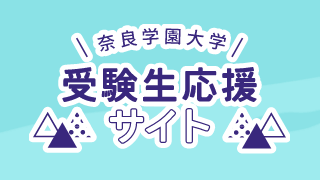7/12登美ヶ丘カレッジ第26回「地球温暖化とライフサイクルアセスメント」を開催しました
7月12日(土)に第26回奈良学園大学登美ヶ丘カレッジ「地球温暖化とライフサイクルアセスメント」が開催されました。今回は、保健医療学部看護学科特任教授の阪元勇輝先生を講師に迎え、地球温暖化の現状と、それに対処するための評価手法についての講義が行われました。
講座の冒頭では、7月に入ってから続く記録的な猛暑や、近年世界各地で頻発する大規模自然災害が紹介され、こうした現象の背景にある地球温暖化の深刻さが指摘されました。特に、温室効果ガスの排出がその主因であることが強調され、1850年から2020年までの間に世界の平均気温が1.09℃上昇したこと、さらにこのまま推移すれば2100年には約5℃の上昇が予測されているというデータが示されました。
続いて、日本の温室効果ガス排出状況についても触れられ、2022年時点で総排出量では世界第5位、1人あたりの排出量では第3位であるという統計が紹介されました。これを踏まえ、地球温暖化によって引き起こされる様々な影響について解説がありました。洪水や土砂災害、農業被害に加え、健康への悪影響も深刻化しており、とりわけ熱中症による死亡者数の増加や、感染症を媒介するヒトスジシマカの国内分布拡大など、日本における「熱帯化」の進行が報告されました。
こうした現状を受けて、講義では環境負荷を定量的に評価する手法である「ライフサイクルアセスメント(LCA)」の概念が紹介されました。LCAとは、製品やサービスが原材料の調達から輸送、製造、使用、そして廃棄に至るまでの全ライフサイクルを通じて発生する環境への影響を評価する手法です。この手法により、家庭での二酸化炭素排出の主な要因がガソリンや都市ガスではなく「電気」であるという意外な結果が示されました。発電時の排出量まで考慮に入れると、電気が家庭全体の排出量の約半分を占めていることがわかり、参加者からも驚きの声が上がっていました。
さらに、LCAの考え方をもとにした指標として、「カーボンフットプリント(CFP)」も紹介されました。CFPは温室効果ガスの中でも特に二酸化炭素の排出量に特化した指標であり、具体例として、40kgのソファー1台の製造に150kgの二酸化炭素が、また1トンの一般的なガラス製品の製造には1,100kgもの二酸化炭素が排出されることが示されました。このほかにも、飲料や野菜、米などの食料品に関するCFPの事例も紹介され、私たちの日常生活のあらゆる場面が環境負荷と結びついていることを実感できる内容となっていました。
講座の最後には、環境問題や生活における具体的な対策について、参加者から多数の質問が寄せられ、活発な意見交換が行われました。参加者一人ひとりが自らの暮らしと地球温暖化との関係を見つめ直すきっかけとなる、実りある時間となりました。




講座の冒頭では、7月に入ってから続く記録的な猛暑や、近年世界各地で頻発する大規模自然災害が紹介され、こうした現象の背景にある地球温暖化の深刻さが指摘されました。特に、温室効果ガスの排出がその主因であることが強調され、1850年から2020年までの間に世界の平均気温が1.09℃上昇したこと、さらにこのまま推移すれば2100年には約5℃の上昇が予測されているというデータが示されました。
続いて、日本の温室効果ガス排出状況についても触れられ、2022年時点で総排出量では世界第5位、1人あたりの排出量では第3位であるという統計が紹介されました。これを踏まえ、地球温暖化によって引き起こされる様々な影響について解説がありました。洪水や土砂災害、農業被害に加え、健康への悪影響も深刻化しており、とりわけ熱中症による死亡者数の増加や、感染症を媒介するヒトスジシマカの国内分布拡大など、日本における「熱帯化」の進行が報告されました。
こうした現状を受けて、講義では環境負荷を定量的に評価する手法である「ライフサイクルアセスメント(LCA)」の概念が紹介されました。LCAとは、製品やサービスが原材料の調達から輸送、製造、使用、そして廃棄に至るまでの全ライフサイクルを通じて発生する環境への影響を評価する手法です。この手法により、家庭での二酸化炭素排出の主な要因がガソリンや都市ガスではなく「電気」であるという意外な結果が示されました。発電時の排出量まで考慮に入れると、電気が家庭全体の排出量の約半分を占めていることがわかり、参加者からも驚きの声が上がっていました。
さらに、LCAの考え方をもとにした指標として、「カーボンフットプリント(CFP)」も紹介されました。CFPは温室効果ガスの中でも特に二酸化炭素の排出量に特化した指標であり、具体例として、40kgのソファー1台の製造に150kgの二酸化炭素が、また1トンの一般的なガラス製品の製造には1,100kgもの二酸化炭素が排出されることが示されました。このほかにも、飲料や野菜、米などの食料品に関するCFPの事例も紹介され、私たちの日常生活のあらゆる場面が環境負荷と結びついていることを実感できる内容となっていました。
講座の最後には、環境問題や生活における具体的な対策について、参加者から多数の質問が寄せられ、活発な意見交換が行われました。参加者一人ひとりが自らの暮らしと地球温暖化との関係を見つめ直すきっかけとなる、実りある時間となりました。